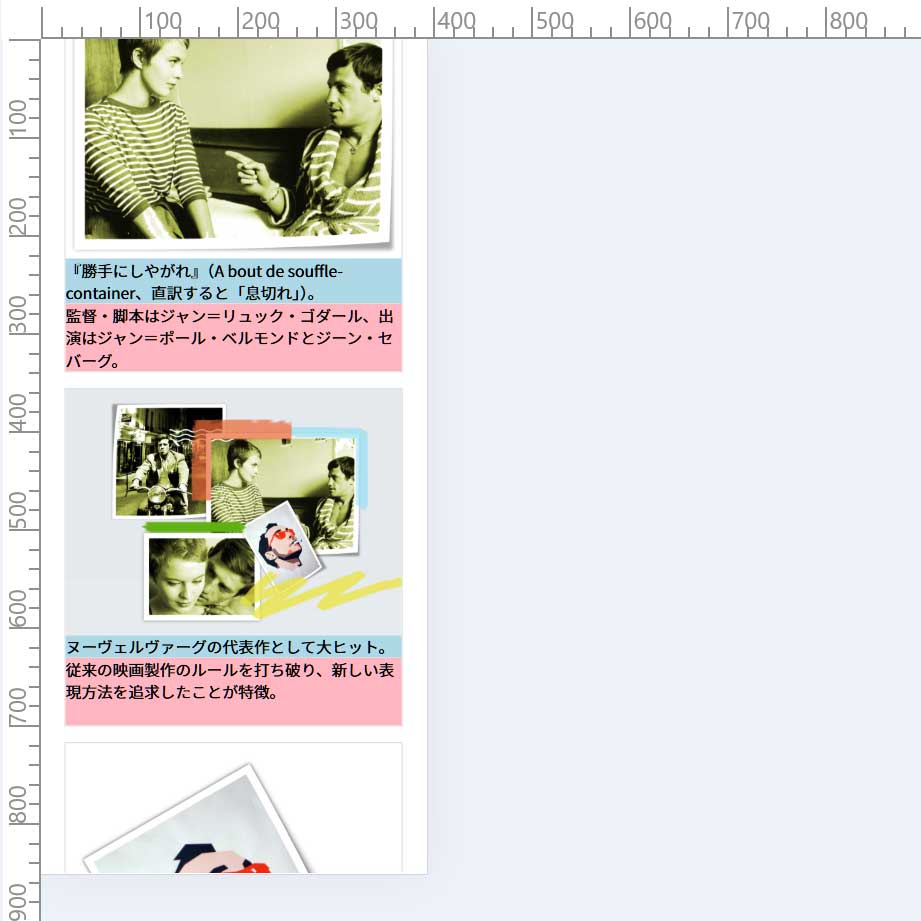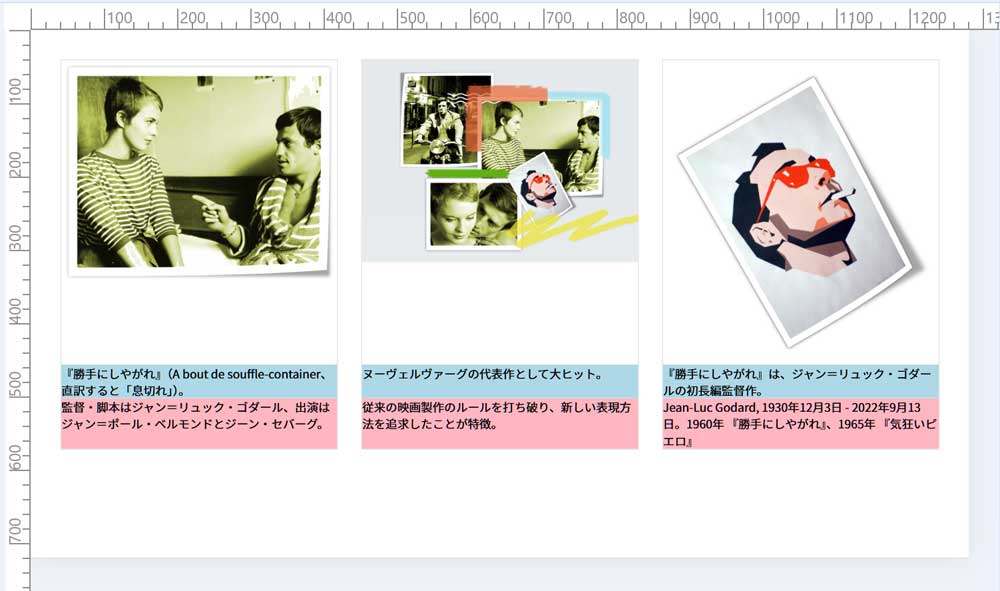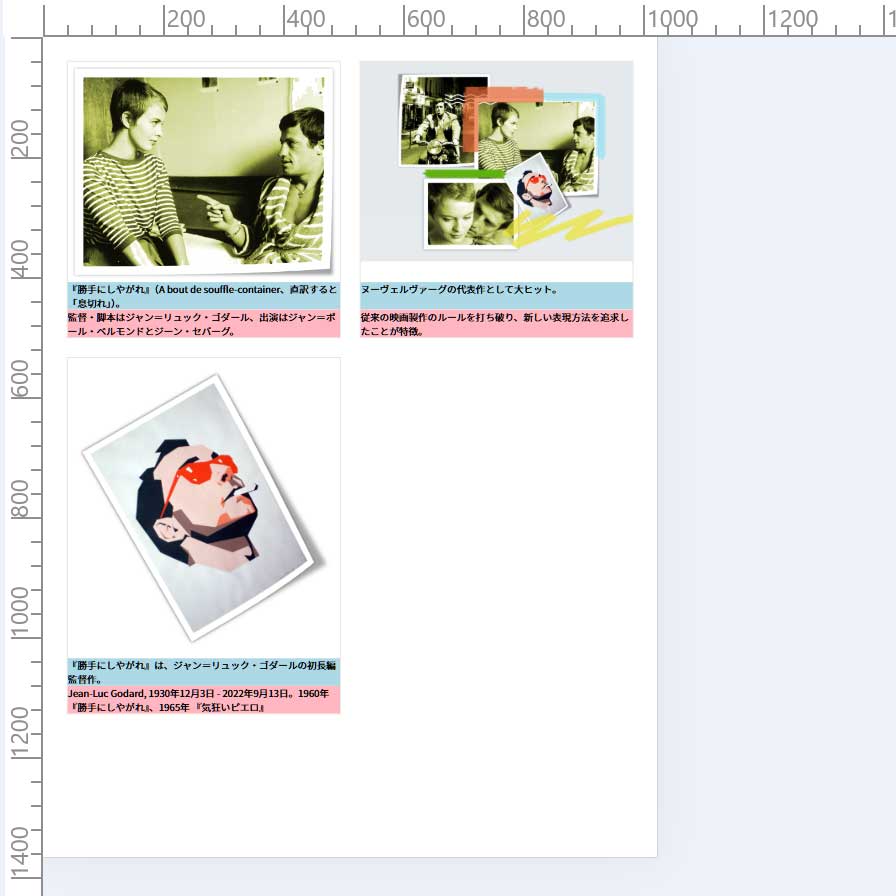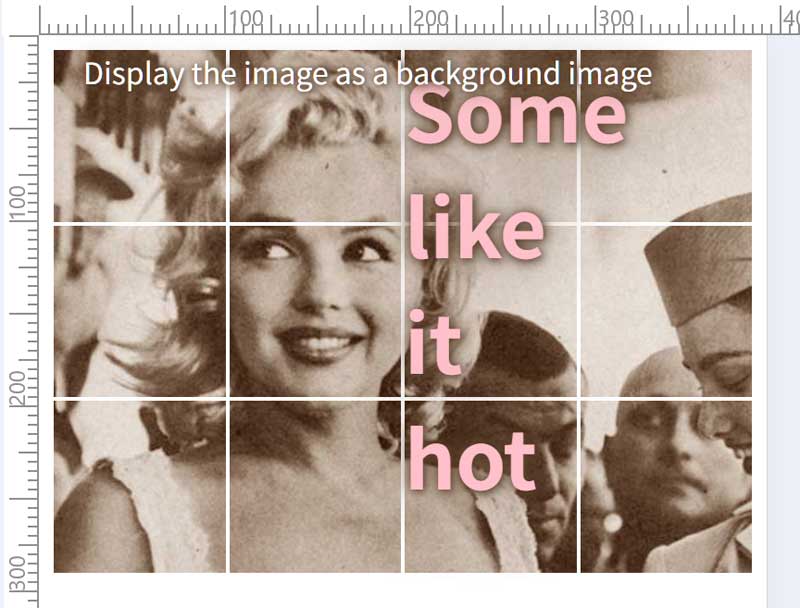グリッドレイアウトの中央寄せ
一般的な中央寄せと幅
一般的に要素を左右中央揃えにしたいとき、使われるのが margin-left: auto と margin-right: auto である。最新のCSSを使うと、より簡単に要素を中央揃えにできる。それが 「margin-inline: auto;」 だ。
くわえて、width: stretch; を確認しよう。width: 100%; に代わるもので、例えば以下のように使う。
.field {
width: stretch;
margin-inline: 16px;
}グリッドでの方法は要素の数で異なる
さて、グリッドレイアウトに於いて中央寄せをする場合、アイテムの数により方法が異なる。方法は place-content: center; と place-items: center; の二つであるが、アイテムの数により使い分ける。尚、このセクションは完全に検証できていない。
具体的に以下に例を提示しよう。
アイテムがひとつの場面
.center.first {
display: grid;
place-content: center;
アイテムが複数の場面
グリッドアイテムとそのアイテムが配置されるグリッド領域の両方とも中央にしたい場合はふたつを併記できる。
.center.second {
display: grid;
place-content: center;
place-items: center;
}